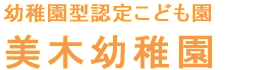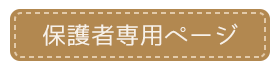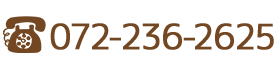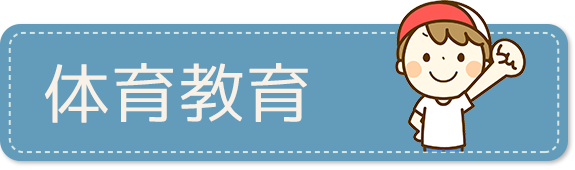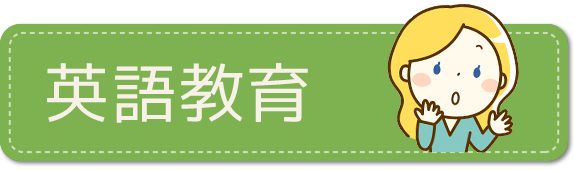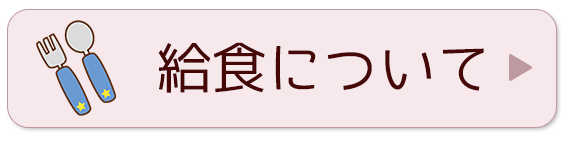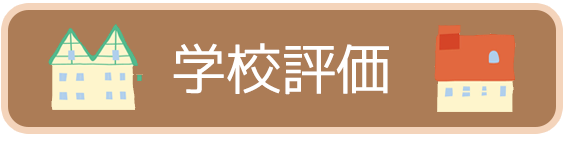令和5年度 学校評価 (施設関係者評価)
1.本園の教育目標
- 健康で安全な生活ができる子どもに教育する。
- 自主的で豊かな創造性を養うために、様々な試みを取り入れ、社会の変化に対応した新しい時代の教育をめざす。
- 多様な教育活動を通じて集団生活に適応できるよう指導する。
- 教育活動には幼稚園と家庭が一体となってあたる。
2.本年度重点的に取り組む目標・計画
「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領」に基づき、子ども一人ひとりの特性を踏まえて、保育活動を展開する。保護者のニーズ、本園の担う役割を知り、教育目標達成に向け取り組みを進める。また感染症予防や事故防止等、一人ひとりの子どもが安全意識を高めながら園生活を送ることができるようにする。
3. 評価項目の達成及び取り組み状況
①一人一人の成長を支援・援助するため、全教職員が共通理解を持ち関わる
全教職員が園児一人ひとりについて、それぞれの子どもに対して理解を深めることが大切と考えてきた。そのために日常的に支援や援助の方法を確認するために、日々のミーティングを活用してきた。また、同様に定期的に子どもの状況について情報交換やその方策について協議してきた。今年度は日々のミーティング(全教職員によるミニ会議)会とともに各学年のリーダーを招集するリーダー会を開催し、各学年の共通理解や情報共有を行うことができた。
②身体を進んで動かし、楽しんで健康な心と体づくりに努める
専門講師を招聘し体操指導を取り入れ、年間計画を作成し体つくりを行った。同様に年間を通じてリトミックを取り入れ表現力や体幹を育む場を設定した。
その上に、外遊びの時間は各学級や学年単位での時間を確保し、狭い園庭ではあるが一人ひとりが思いっきり駆け回れる空間を用意することができた。様々な種類の遊具で走ったりとんだりと友だちと協力しながら楽しんで遊ぶ姿が見られた。
③ことば・文字にふれる機会を増やし、表現力を伸ばす
昨年に引き続き、年少初期から積極的に絵本や紙芝居などの読み聞かせの機会を増やし、言葉集めなど語彙を増やす取り組みも行った。そのために、園児が使用する文字練習等の教材を厳選したり、新刊絵本等もできるだけ購入量を増やしたりしてきた。文字を書く練習は一人ひとりの習熟に合わせてきめ細やかに指導することにしてきた。
④規則正しい生活習慣を身につける
「あいさつ」については、昨年同様に園生活の場や登降園時に保護者と子どもに声かけをかかさず行ってきた。同様に、学級の保育・教育の場でも、入園相談・見学や幼稚園来客者に対しても、気持ちの良いあいさつができるよう指導してきた。
子どもに対しては、日々の幼稚園生活が、規則正しいリズムで過ごせるようメリハリをつけて保育内容を工夫してきた。朝の登園時刻については間に合わないご家庭もあり、月のしおり等で啓発してきた。
⑤行事等を通して、協同性や自立心を養う
コロナ禍以前に実施していた「バザー・模擬店」が第5類になったとはいえ、感染症予防の観点から実施困難であると考え、新しく「みきっこ広場」を新設した。みきっこ広場・運動会・遠足・お遊戯会などの行事は、感染症予防を継続しながら、一人一人が協力し、みんなで作り上げる喜び、達成感を育成する良い機会となった。また、内容は子どもの満足感・充実感のある活動になるよう工夫して行った。一つ一つの行事の中で子どもが活躍できる場を意図的に設定し実践してきた。
⑥園での子どもの様子を、保護者と共有する
毎月のしおり、学年だより、ホームページを通して活動内容や保育・教育の様子を知らせてきた。保護者への情報発信として「子育てのWA!」を毎月作成した。内容は、「子育てのあれやこれや」を中心に子どもとの触れ合いや絵本コーナー、食育に関連したものを提供してきた。
ホームページは、一日一日の子どもの様子がわかるように「今日の一コマコーナー」を新設し、ほぼ毎日掲載してきた。「月のしおり」については、読みやすさを求める声もあり、A4判からB4判に改良し、文字の大きさも工夫するようにしてきた。
⑦英語活動を通して、国際感覚を養うとともに、コミュニケーション能力を高める
英語指導は、身体表現やゲームを取り入れ楽しく英語を学ぶ機会となった。子どもたちは毎週英語指導の時間を楽しみにしていた。卒園時には、少しではあるが簡単な質問の受け答えができることをねらいとしていたが、「身体表現や遊び、ゲーム」を通して会話力を育むまでにはいかなかった。
4.総合的な評価結果
年度末に子どもの様子、幼稚園の教育、家庭での様子という観点から、保護者アンケートを実施した。そのことにより園や子どもに対する保護者の思いや考えがより明確になった。その集計結果から教職員間で検討と共有を行い、その第一次まとめを全保護者対象に公表した(3月16日、22日)。
その後、さらに教育目標の達成状況の把握と整理を行い、明確になった課題等については、令和6年度の保育・教育実践に生かすとともに幼稚園型認定こども園として保育や教育の両面についても、さらに経験別・課題別の研修等により力をつけ、日々の実践に生かしていくことが重要と考えた。
5. 成果と課題、方向性
①一人ひとりの成長を支援・援助するため、全教職員が共通理解を持ち関わる
日々のミーティング・定期的に子どもの状況について情報交換やその方策について協議に加え今年度から月1回のリーダー会や日々ミーティング(ミニ職員会議)を取り入れたことにより各学年の共通理解や情報共有を綿密に行うことができた。その結果、個々の子どもに対する対応・指導により一貫性が見られるようになった。次年度から、子どもたちの成長を支援・援助するために特別支援コーディネータを配置する。
②身体を進んで動かし、楽しんで健康な心と体づくりに努める
専門講師による体操指導に加えリトミック指導を取り入れることにより、一人ひとりの体力が向上してきた。1日に2回の園庭での遊びの継続による効果もあった。また、運動遊びの後の手洗い・消毒等、感染症予防の習慣も身についてきた。
③ことば・文字にふれる機会を増やし、表現力を伸ばす
毎週正課の中で語彙を増やすことや文字の読み書き等ができることをねらいに教材を使用している。学級の担任・副担任によるきめ細やかな指導で集中して取り組む姿勢が身についてきた。しかし、語彙力や自分の思いをうまく伝える、一つの言葉からさらに思いを巡らし広げていくということについては課題が残る。
④規則正しい生活習慣を身につける
幼稚園生活のあらゆる場で「あいさつ」について、来園者から「美木幼稚園の皆様が子どもまで挨拶をしてくれて気持ちがいいですね」、と言われるようになってきた。今後も家庭と連携し、日々取り組んでいき、単なる「あいさつ」から気持ちを込めて言えるようにしていきたいと考える。規則正しい生活リズムは家庭との連携が必須である。特に朝の登園時刻や一日の保育でリズムがつかみにくい子どももいるので、引き続き啓発と家庭との個別対応を取り組む必要がある。
⑤行事等を通して、協同性や自立心を養う
新設の「みきっこ広場」では親子・卒園生との交流もできた。それぞれの行事の中では特に子どもが主役にすることを中心に実践してきた。また、年長組では各行事の中でできるだけ多くの園児にリーダー役を経験させた。その結果、存在感を持ち、みんなで作り上げる喜びや達成感を味わわせることができた。次年度も同様の方向で臨みたい。
⑥園での子どもの様子を、保護者と共有する
「月のしおり」については、A4判からB4判に改良したが、読みやすさについては文字数も多くまだまだ掲載の仕方等に工夫がいる。ホームページは、今日の一コマを新設し、アンケートのご意見欄でも好評であった。今後はさらにいろいろなツールを活用して、様子が分かるよう工夫していくこと必要である。配付物をBrain園児アプリを活用しスマホ等の機器でも閲覧できるようにし、園からの情報を身近に感じてもらうようにする。
⑦英語活動を通して、国際感覚を養うとともに、コミュニケーション能力を高める
身体表現やゲームを取り入れ楽しく英語を学ぶことを継続しながら「会話力を重視した指導」を展開するために、新年度から、新たなカリキュラム・新たな講師を招聘して英語活動に取り組むようにする。幼児なりの会話力の育成を図っていく。
⑧その他
〇教育・保育の質及び職員の資質向上のために、行政機関や幼稚園連盟等の研修会には全教職員が積極的に参加し、日々の保育・教育の実践に生かしていく。研修で得た成果については、全職員が共通理解し積極的に取り入れていく。取り組みは、一つのクラスだけではなく、全園児に対し率先して行う。
〇大切な命を守るために、一人ひとりの子どもが感染症をはじめ、身の回りに起こりうる危機回避や安全意識を高めながら園生活を送ることができるようにする。園の送迎バスは、人的ミスが起こらないよう安全管理の為のシステムを構築しているが、更にBrain園児アプリ等を活用し安全確認を徹底する。
〇学年ごとの発達段階を踏まえ、1年間の四季折々の季節感を味わい、園生活に変化や潤いを感じさせる行事を精選し創造する。安全に楽しく、子どもたちが充実感や達成感・成就感を持てるよう工夫する。
〇教育目標の一つ「社会の変化に対応した新しい時代の教育をめざす」について、今では、英語・体操等はどこの園でも取り組みが進んでおり、質の問題になってきている。令和6年度から英語活動は、会話力を重視した指導に転換していく。また、時代の流れから、体幹も鍛え、楽しく身体活動ができる、ダンスを正課の中で取りいれていく。
6. 学校(施設)関係者の評価
今年度も引き続き、保護者のアンケート結果から学校評価を丁寧に行い、日々の保育・教育を改善していこうとする姿勢は評価できる。また、それぞれの質問項目に対して、ほとんどが90%以上の肯定的な回答であったことは評価できる。
以下、「自己評価」のそれぞれの観点に沿って、評価を行った。
①一人ひとりの成長を支援・援助するため、全教職員が共通理解を持ち関わる。
どの先生方も子どもの特性をよくつかんでいることは、園を訪問する毎に感じることが多い。会議で先生方が全園児の情報(名前・顔・個性)を把握していることは、日々の様子から実感で
きる。先生方が子どもに関心を持つことで「バスの置き去り事故」などを未然に防ぐことにも繋がるため、今後も継続が必要。
来年度より特別支援コーディネータの配置を実施していただけることは、子どもたちの成長支援につながるのでぜひお願いしたい。
②身体を進んで動かし、楽しんで、健康な心と体づくりに努める。
日々、日課の中で、園庭遊びを位置付け、ののびと身体を動かすことを実践していることは評価する。時期によっては健康被害防止も考えながら継続してもらいたい。
子どもから幼稚園の話を聞く限り、ほとんどの園児はお外遊びやリトミックなど楽しんでいると思われる。子どもの楽しみでもあるので、梅雨時でもお遊戯室などを活用して対応可能な運動(遊び)を積極的に取り入れて欲しい。
③言葉・文字に触れる機会を増やし、表現力を伸ばす。
新刊絵本等もできるだけ購入量が増えたことはこどもにとっても好ましいことである。「読み書き」など特に文字を書く練習は一人ひとりの習熟に合わせてきめ細やかに指導してもらっているが、個人差が出ることをもあるので、子どもたちが苦にならないように配慮することが必要。言葉集めについては、子どもからの会話で実感できるため、絵本などの読み聞かせの機会を増やすことを継続してほしい。
④規則正しい生活習慣を身に付ける。
園児たちも元気に挨拶している光景をよく見かける。委員が訪問した時も笑顔で対応、あいさつをしてくれる子どもが増えてきたように思う。登園、降園時の挨拶について積極的に取り組んでいると評価できる。幼稚園は子どもたちに社会生活のルールを学ばせる場でもあるので、登園時間に間に合わない一部のご家庭については、月のしおりなどで間接的に伝えるのではなく、事情等も聴きながら直接改善要請をすることが必要である。
⑤行事等を通じて、協調性や自尊心を養う。
新設の「みきっこ広場」での卒園生や保護者との交流は、親子で半日を楽しく過ごせる機会となっていることや卒園した子どもたちの成長を知る機会となり意義がある。一つの行事に向けて目標を持ち、その経過(協力・信頼)を大事にすることで達成感や成就感、リーダー育成につながっていると感じられる。
保護者にとっては行事を通じて園児たちの成長を感じる良い機会であり楽しみなものではあるが、2学期以降は各行事間が短いのではと感じる。成果も多くあるが、子どもたちからすると覚えることが多くあり、疲れ(心も身体も)のようなものはないか心配である。例えば、行事間に芸術鑑賞など受動的な活動を入れる等、四季折々季節感を感じながら潤いのある幼稚園生活を送るという観点も入れながら、年間通じて行事を見直し精選をする機会も必要ではないか。
⑥園での子どもの様子を保護者と共有する。
様々な方法で情報発信に力を入れ、適時改善(今日の一コマなど)している事は評価できる。継続して読みやすい工夫を行ってほしい。また配布物を「Brain園児アプリ」による閲覧に切り替える方向性は、資源ゴミの削減の観点等から非常に評価できる。
Instagramについては、だれでもいつでも閲覧できる利点があるが、その反面、子どもの個人情報の掲載について課題(顔、人物の特定など)があるので、慎重に対応してもらいたい。
折角、アプリ等で情報発信しても、既読にならないご家庭があると聞くが、個々に対応を求めて全保護者が共有できるよう努める必要がある。
⑦英語活動を通じて、国際感覚を養うとともにコミュケーション能力を高める。
これからの時代、園児にとっては英語に触れることが大切、そして楽しく学べる事が重要と考える。「会話力」について指導内容を聞くと、実際には子どもたちの大好きな身の回りの物を題材にして英語で学ぶ、ゲームや身体表現を通じて学ぶなど、工夫を重ねて楽しい活動にしながら実施していることに安心した。その結果、身につくものとして「簡単な日常の会話、幼児の発達段階に合わせた力」ということがわかった。無理して会話を教え込み会話力を付けるものにならないように注意が必要である。活動を継続しながら園児の反応を見て「楽しい」を重点になるよう日々改善していって欲しい。
⑧正課の中での活動「ダンス」を実施する方向について
新しい時代に対応した活動で、正課の中で多様な活動を取り入れていることは、楽しく協力して一つのものを創り上げていく、楽しく身体表現をするなど、子どもたちの教育にとって好ましいものと考える。旧態依然の体制だけではなく常に社会の情勢を見ながら対応していくことは重要である。但し、不易なもの、時代が変わっても大切にしていかねばならないものについては、継続して指導していく必要を忘れてはいけない。
【最後に】
美木幼稚園は立地等の利便性も含め、『教育目標』に賛同し決めている方も少なくないと思われる。子どもの自主的で豊かな創造性を養うことや、集団生活に適応できるように指導することなどに加えて、安心して預けることができる環境の提供が重要である。取り巻く周辺環境などにも恵まれており、その点安心していただけることができると評価できる。また年度ごとに重点目標並びに計画を組み立て、先生方が一丸となって、園児たちに関わっているところは、様々な情報発信を通じて取り組み姿勢に共感できる。
美木幼稚園を卒園している保護者も多く、良き伝統は受け継がれていると感じている。傍百貨店の企業メッセージのように(変わらないのに、新しい)そのような運営を継続していってほしいと思う。
以上、保護者の皆様からのアンケート、学校(施設)関係者の皆様からのご意見・提言をいただきありがとうございました。幼稚園の自己評価と合わせて令和6年度以降の運営の参考にさせていただきます。